今回のこんな人は、土田昇さんです。「刃物店店主」の方です。こんな方(失礼な!)も、こういう場に呼ばれるのだと、感じ入った次第です。どんな刃物を商売されているのかは、HP見れば分かるのしょうが、私の大学時代の担当教授も1回だけこの「みすず」に顔を出されたことがあったことも、懐かしく思い起こしました。今、どうしておられることか、思います。
土田氏が紹介されている本は、高田良信『近代法隆寺の祖 千早定朝管主の生涯』(聖徳宗総本山法隆寺 1998年)についてです。が、この本、アマゾンで探すに、「英語版」とあります。「日本語版」を見つけることができません。どういうことだろうかと、疑問です。
で、この本に対して土井氏のコメントは、
明治時代、法相宗の独立した本山としての認可を得るため、奈良産の墨と森川杜園作の「奈良木偶」等を土産に嘆願した話など興味深く、またフェノロサや天心らが二〇〇年ぶりに開扉した秘仏、救世観音について、記録好きの定朝管主がその日本美術史上の事件について何も書き残していない、と平成の法隆寺管主はしるす。
以上です。
文化庁(?)に賄賂を贈った話もですが、秘仏・救世観音について、日本美術史上どころか、仏教史上、それこそ法相宗派史上ものすごい大変なことをフェノロサと岡倉天心がやってしまったにもかかわらず、それについて何も書き残していないとは。大きな事件すぎて何の口出しもできなかった、口にしたくなかった、思い出したくもなかったのだろうか。ショックすぎる出来事は、えてしてそういうものかもしれないですね。「それにしても!」ではありますが。
実は、そのことよりもここで私の脳裏に浮かんだのは、一枚の救世観音様の写真と、梅原猛・元MIHO MUSEUM館長の1972年5月刊行の「隠された十字架」(毎日文化賞受賞)です。
アマゾンの紹介部にはこうあります。
法隆寺は怨霊鎮魂の寺!
大胆な仮説で学界の通説に挑戦し、法隆寺に秘められた謎を追い、古代国家の正史から隠された真実に迫る。
門の中央を閉ざす柱、一千二百年の秘仏・救世観音――古の息吹きを今に伝え、日本人の郷愁を呼ぶ美しき法隆寺に秘められた数々の謎。その奥に浮かび上がる、封じ込められた怨霊の影。
権謀術数渦巻く古代国家の勝者と敗者を追い、あくことを知らぬ心理(ママ:筆者)への情熱と、通説を打破する大胆な仮説で、ときの権力により歪曲され抹殺された古代史の真実に華麗に挑戦する、「梅原日本学」白熱の論考。
今から50年近く前の高校生だった私は、もちろんこの広告文に魅せられたわけではなく、新潮社からの文庫本(1981年刊)もまだ発売されておらず、ただ、高校の国語担当の渥見秀夫先生の一言「推理小説みたいに面白いで!」で、この本に飛びついたのでした。
そして、大学に入って友人と奈良に遊んだ時に、法隆寺にて一枚の救世観音様の御尊影を買い求めたのでした。仏像の写真を買う習慣などない大学生の心を動かしたのは、やはり、梅原先生のショッキングな「十字架」のせいです。その十字架を背負っているのが、聖徳太子の等身大といわれている救世観音様なのです。
本当にすごい迫力満点の観音様なのですが、私はその御尊影を下宿のアパートの本棚の側面に貼って、朝晩拝んではいませんでしたが、不思議なことが起こったのでした。その内容については、また、noteに書きたいと思いますが、「わらしべ長者」のようなことが起こりました。彼も観音様に祈ったのですから、ありうる話でもあるのですね。
今日は、このあたりで。
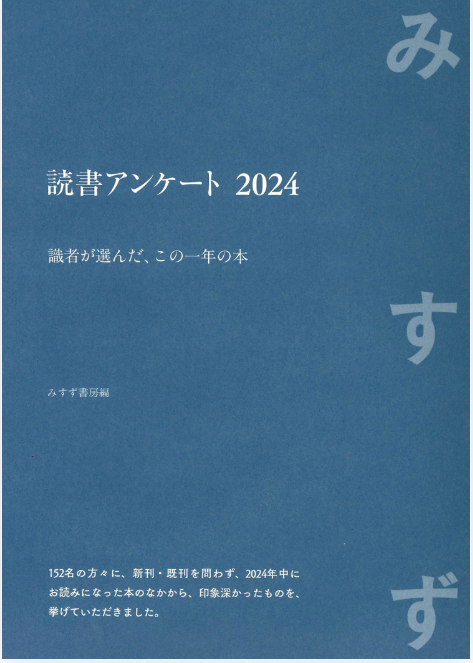

コメント