ゲイブ・ブラウン 著「土を育る 自然をよみがえらせる土壌革命」
レイモンドさんは、北海道に住むアメリカ人です。
メイビレッジ長沼という会社の代表で、メイナイト協会に所属されており、かなりな活動家、理論家、実践家の方です、など私が紹介するまでもないと思います。
今回は、秀明自然農法ネットワーク(SNN) |の主催で、氏の講演会を聞くことができましたので、その報告です。
1995年に、掲載していますゲイブ・ブラウンさんの本を読んで、有機農法から土を育てる不耕起農法に変えられました。それによって、微生物の働きにより、大地が再生していることを感じられ、2040年までには、40%の農家がこの農法を実行するという目標を持たれています。
その諸原則は、以下の通りです。
① 周りの状況を把握する。- 土の状態、気候、農場を取り巻く状況、持っている機械、地域、なぜ農業をするのか
② 土をかき乱さない - 化学的攪乱と耕作を最小限にする。無肥料・無農薬。不耕起・省耕起 思慮深い耕作、土壌微生物の破壊を最小限にする
③ 土壌が被覆されている状態を保つ 草や有機物による地表の被覆と保護
④ 多様な生物(植物)の共存 - 地上の植物の多様性は地下の多様性(様々な根、土壌微生物)を生み出すために必要である
⑤ できるだけ年間を通して、土中に植物の生きた根を維持する(生きた植物の根が伸びる土壌)
⑥ 可能であれば、農場に家畜を組み込む
⑦ 何を取り除きたいかではなく、育てたいものにフォーカスする
以上。
これは、ゲイブ・ブラウンの提案に、レイモンドさんが⑦を付け加えられたものです。
まったく、私はこれらを実践したくてたまらなくなりました。
レイモンド氏は、慣行農法からのパラダイムシフト(当たり前を変える)ことが、農業においても必要だと説かれます。テクノロジーや経済に頼り、足りないもの埋めていくのではなく、問題は自分の中にあり、認識や理解の仕方を変えることの必要性に気付くこと。このシフトが、思想の枠を超え、経済と政治を巻き込み、一人ひとりの生き方を輝かせ方向に行くことを、私も私の圃場で、職場で、地域で、行っていきたいと考えます。
その大地公再生のパラダイムを、レイモンド氏は、次の8点にまとめられていました。
① 農業は自然の一部であり、自然との調和の中で共存することが原則である。
② 自然は私たちのガイドであり保護者である。
③ 病害虫は自然のゴミ収集車であり、雑草は自然の世話人である。
④ 土壌は生きており、ダイナミックである。
⑤ 自然は秩序をもち、知性があり、完全である。
⑥ 自然は従うべき手本である;自然界の植物、土壌、動物は理想的な特性を備えている
⑦ ホリスティック - 全体は部分の総和よりも大きい(生物学的フィードバック・ループ)
⑧ 非線形 - 調和、相乗効果、観察に基づいている。
以上です。
日本時としては、「なんだか当たり前。今頃、気づいたの。」感が拭えませんが、デカルト以来の西洋思想においては、画期的なパラダイムシフトなのだと思います。
秀明自然農法の創始者、岡田茂吉師は、「自然尊重、自然順応、自然がすべてを教えている」と言われます。私もそんな生き方を半農半教員として、していきたいと思いました。
昨年は、堤未果さんの「ショック・ドクトリン」のお話でしたが、今年も本当に刺激的な講演会でした。来年も楽しみです。

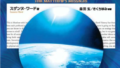

コメント