やっと、1ページ目から読み始められました。本当に、なかなか、前向いて進まないというか、この本は、始めから根詰めて格闘する種類のものではないと思うのですけれど、私の場合はこの36年間、必死に、読み込んだ経験があります。どんな本をインテリさんたちは読んでいて、次に私が読むべき本は何なのか、必死に読んで探してきた。不安だったから? そう、でも、もはや十分アカデミズムの世界からは取り残されている県立高校の国語の教員(失礼な!)ではあるけれど、少なくとも、目の前の生徒には、なるべくホッとな情報を提供して、一緒に考え、楽しみたかったのです。
だから、ほかの人がどのような受容の仕方をしておられるのかは、正直、分からないけれど、私は、ある程度丁寧に今は亡き「みすず 1/2月合併号」を熟読してきました。
そこで、今年の152名の「知識人」(とお呼びしていいと思うのですが)の方々の2段組180ページから頂いた情報をもとに考えたことを、芋づって見ようと思うのです。
で、今回は(いつまで続くか分かりませんが)とりあえず、一先ず、24,25pを取り上げてみようと思います。
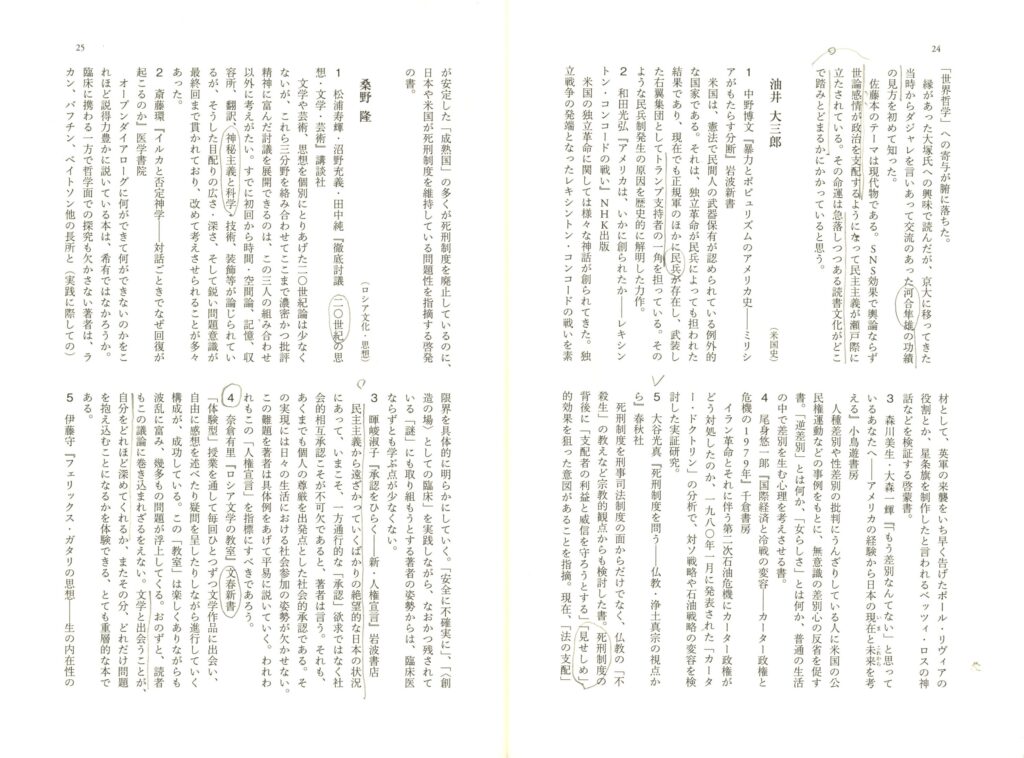
1 佐藤文隆氏(理論物理学)が回答されたアンケートから
① 「京大に移ってきた当時からダジャレを言いあって交流のあった河合隼雄の功績の見方を初めて知った」とあって、その紹介されている本を読めばこの「功績の見方」という表現が面白くって、「いろいろな功績を残された方のなのだな」とは納得できるものの、今のところ私にはその内実がよくわからない言い回しなので、気になりました。
が、ここではそこではなくて(「ここ」「そこ」と老いた夫婦の口喧嘩(笑))、河合隼雄。
懐かしいのです、ご在世中に一度、お目にかかったことがありますが、何といっても日本におけるユング紹介者、研究者として、私は40年前の大学時代からお世話になっている方で、最近では、小川洋子さんとの対談本「生きるとは、自分の物語をつくること」(2011/2/28)で久しぶりに隼雄節に触れまして、自分も「自分にふさわしい自分の物語」として「稲作創話 棚田物語」を、noteに書き始めたりしたのでした。
② また、「SNS効果で輿論ならず世論感情が政治を支配するようになって民主主義が瀬戸際に立たされている。その命運は急落しつつある読書文化がどこで踏みとどまるかにかかっていると思う。」というくだりを読んで、この「みすず」で栃木祥氏が「大衆が全体主義に同調していく様が胸をえぐるのは「今」に重なるからだ。改めて「衆愚」という言葉の意味を考えさせられる。」(22p)と言われていることが、正しく重なりました。また、佐藤氏の次に採られている油井大三郎氏が「暴力とポピュリズムのアメリカ史」(岩波新書)を紹介していることとも、偶然ではないように思えてきました。
更に、栃木氏は「気が塞ぐばかりの世界情勢」、油井氏の次に上がっている桑野隆氏は「民主主義から遠ざかっていくばかりの絶望的な日本の状況」とも書かれている。本当に今年、世界は、日本は、どうなっていくのでしょうか。大きな時代の転換点ではあるのでしょう。
そんな中、「読書文化がどこで踏みとどまるか」ですが、公立図書館が消えていっている昨今、この「みすず」には、「舟橋図書館の新着図書の棚で手にしたもの」のみを5冊、挙げられている方(永田洋氏 41p)もいらっしゃって、しかも氏が挙げられている5冊が、ポランニー、バトラー、パウル・ベッカー、マックス・ウェーバー、吉田健一についての書籍で、全く、この図書館の司書の方には脱帽し、すごい公立図書館もあるものだと、感嘆し、勇気づけられた次第です。
2 油井大三郎氏(米国史)が回答されたアンケートから
① 先述の「暴力とポピュリズムのアメリカ史」の紹介文の中で、「トランプ支持者の一角を担っている」「民兵=武装した右翼集団」に触れられていますが、そのすぐ前の下りで、「独立革命が民兵によっても担われた」とあり、やはり、今期のトランプ大統領がしようとしていることは、改革ではなくて「革命」なのだと、油井氏と共に(?)納得した次第です。
② 大谷光真『死刑制度を問うーー仏教・浄土真宗の視点から』は、油井氏のみならず、26pの堀川恵子氏も「最小限の言葉で、最大を著す圧倒的な筆致」と絶賛されています。死刑制度については、毎年誰かが「みすず」の中で取り上げていると記憶しています。ここに、日本やアメリカの「支配者の利益と威信を守ろうとする」姿勢や、後進性や野蛮性を見ようとしているのでしょう。だから「敵討ち」容認など、とんでもないことなのだろう。私も、信仰者としてこの本は読んでおきたいと思います。
3 桑野隆氏が回答されたアンケートから
① 松浦寿輝・沼野充義・田中純一『徹底討論 二十世紀の思想・文学・芸術』を紹介されて、そこで取り上げられている内容の中に、「神秘主義と科学」があることを知り、現代にこのことをどう論じているのか、本当に知りたく思いました。スピリチュアルと深層心理学、ユングやニーチェ(私の中では、ユングもニーチェも瞑想者です)、この「みすず」や岩波の「図書」と「アネモネ」や「ムー」を、どこまでカバーしてくれているのか、知りたいのです。期待して、取り寄せます。
② 「文学と出会うことが自分をどれほど深めてくれるか」を体験できる重層的な書物として、奈倉有里氏の「ロシア文学の教室」(文春新書)を取り上げられています。高校国語の教師として40年間生きてきて、ここに至っての文科省の文学軽視の学習指導要領改悪の暴挙を腹立たしく思っている身にとっては、正にこの新書を拝読し、生徒に紹介したいと思ってしまいました。人は「自分にふさわしい自分の物語」を作り上げるために生きているのですから、その大いなるお手本を知らずして、どう生きればいいのでしょうか。今から、漱石の「こころ」も、鴎外の「舞姫」も、中島敦の「山月記」も、小林秀雄の「無常ということ」も読んだことのない医者や弁護士や教員が増えていくでしょう。まったく「急落しつつある読書文化がどこで踏みとどまるか」、ここでも「気が塞ぐばかりの」「絶望的な日本の状況」なのではないでしょうか。
とまあ、ほぼ2ページを駆け足で見てきただけでも、私への刺激度はマックス。これが、180p続くのですから、大変なごちそう。そして、毎年、消化不良を起こしまくって、今年もまた来年の「みすず」を迎えることになるのでしょう。
そんな「みすず」の需要をしている芸農家のつぶやきでした。少し長すぎましたが。
次回、気が向いたら、②を書きます。
よろしくお願いします。
ここまで、読んでくださってうれしいです。
ありがとうございました。
では、また。
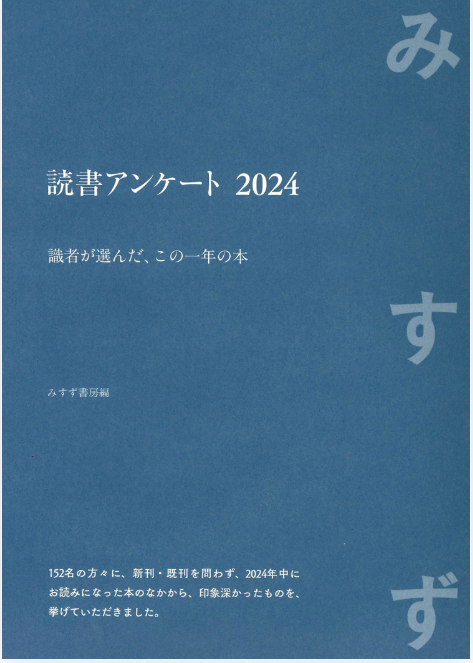


コメント