詳しくは、稲作創話「棚田物語」甲類02「わらだし」をご覧いただきたいのですが、今回お話ししたいことは、その中でも特に②「なぜ田外(でんがい)に藁を出すのか」ということです。
「棚田物語」には、
「薬を使わない自然農法の田で藁を田中(でんちゅう)に残してしますと、土中で腐った藁が有毒ガスを出して稲の成長を妨げるので、藁は、田から出したいのです。」
と書きましたが、この「有毒ガス」が、メタンガスで、田中だけではなく地球に対してもいろいろと悪さをするようです。そのことを、このグログの1回目にも登場していただきました堤美果さんが、同じ「国民の違和感は9割正しい 」で言われてますので、それをご紹介したいと思います。
堤さんによると、「漁業と農業を犯罪化する「エコサイド法」」が成立すると、「〈気候変動〉の名の下に、農業を犯罪化」できる、らしい。
2024年のダボス会議の「気候と健康」の分科会で、モンサント社を傘下に持つドイツの化学大学バイエルン社のCEOビル・アンドーソン氏が、「米の生産はメタンガスの最大の発生源の一つであり、温室効果ガスという意味では、二酸化炭素の何倍も有害だ」との発言を受けて、堤さんは、
「たしかに、農業が出す温室効果ガスの18%は稲作由来。そしてまた、アンダーソン氏の言うように、水田の底の泥からCO₂の28倍の温室効果を持つメタンガスが発生するのは事実です」と言われて、その解決策の一つとして、魚を水田に放つことを揚げておられます。
実際、以前、NHKで見た中国の奥地の想像を絶する棚田での稲作をしているところでは、その棚田で鯉を飼ってました。お米の収穫後は、それを食べる。
それを見た私は、棚田の規模のすごさに圧倒されるとともに、「たしかに鯉は、ジャンボタニシの天敵だし」と思い、まさに「一石三鳥」(堤氏)以上だなぁと、思います。
で、さらに、藁を田中から出せは、水田から出るメタンガスは、明らかに減少します。
そして、私は、出した藁は今のところ積み重ねて堆肥にして、苗立ての床土にしていますが、昔なら、耕作用に飼っている牛の餌でしょう。実際に私が小さい頃は、田舎の祖父の家に牛小屋がありました。
また、稲をバインダーで刈って十束たばねたら、買い取り業者が、鰹のたたき用に一束100円で買ってくれるといううわさも聞きましたので、そちらにも挑戦しようと思っています。無肥料、無農薬の育てて藁ですから、さぞかし旨い鰹のたたきになろうかと思います。
というように、藁を田中から出すことへの意義は、お分かり願えたと思います。
そして、堤さんの本では、この話の後に、ヴァンダナ・シヴァ博士(インドの哲学者で、種の保存を行っているナブダーニャ財団代表)の「在来種子」の保護と活用の重要性の話を揚げられており、その後に、本ブログ1回目の話につながるのですが、その話は、又にしたいと思います。
というのは、実は私は、シヴァ博士の講演を何回か直接に拝聴できたのみならず、私が勤めている学校へも来てくださり、校内のチャペルで生徒たちにも、ご講演頂いたことがあるからです。(どや!!)
って、それより、種の保存のために、SNN(秀明自然農法ネットワーク)がシードバンクを作った話の方が大事でしょ!!!
ちょうど時間となりました。
おあとがよろしいようで・・・。

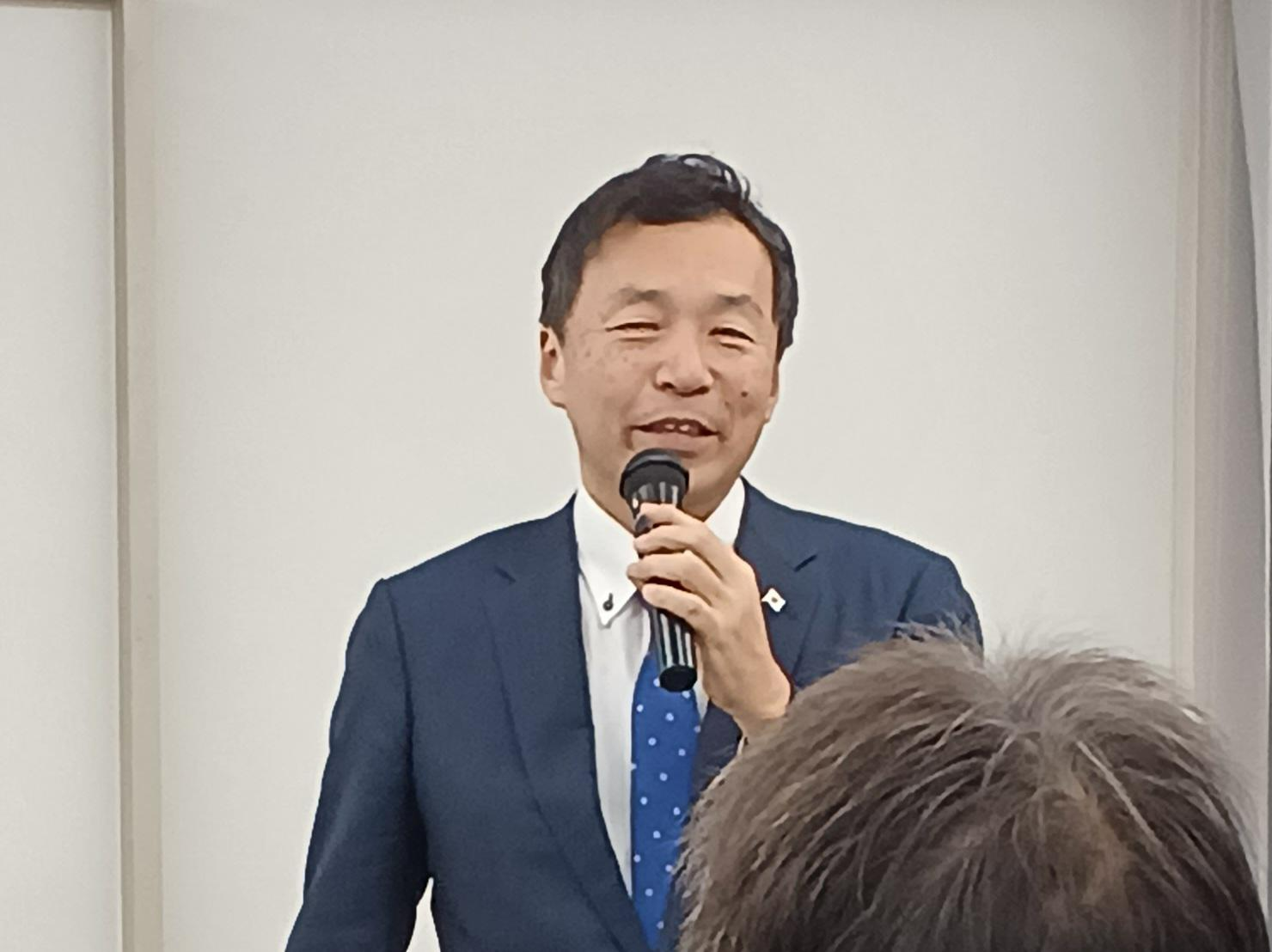

コメント